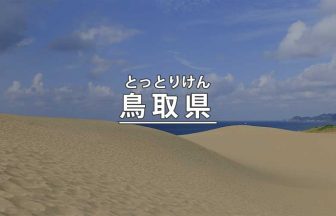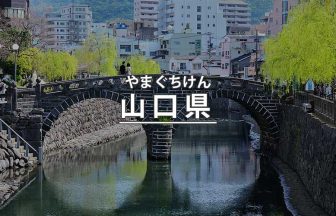島根県は中国地方の中部、広島県の北部、山口県の東部に位置する県。 島根県を代表する観光スポットといえば、縁結びの神様がいる「出雲大社」。 実は、それだけでなく国宝「松江城」、日本一の庭園に選ばれ続けている「足立美術館」、世界遺産にも登録された「石見銀山」など素晴らしい観光スポットがたくさん。 温泉も、神の湯「玉造温泉」、「温泉津温泉」など良質な温泉が数多く湧出している。
おすすめ温泉 ご当地グルメ 定番のお土産 島根県の名産・特産
「出雲大社」は、島根県出雲市大社町杵築東にある神社で、島根県随一の観光スポット。日本一の縁結びの神様として全国的に有名な大国主大神が祀られている。縁結びは、男女間に限らず人々を取り巻くあらゆる繋がりのご縁を結ぶものとされ、初詣や祭礼の時期には、縁結びや開運のお守り、ご朱印を求める多くの人が訪れる。旧暦10月は、「神無月」といわれるが、出雲にはたくさんの神様がやってくることから、「神在月」といわれる。
「松江城」は、島根県松江市にある、1611年に堀尾吉晴により築城されたお城で、国宝にも指定されている松江市のシンボル。城の外壁の大部分が黒塗りの下見板張りである見た目から別名「千鳥城」とも呼ばれる。堀川には観光遊覧船があり、城下町の風景を楽しむことができる。茶室でお茶と共に和菓子をたしなんだり、土産物店などを散策することができる。
「足立美術館」は、島根県安来市にある美術館。17年連続で庭園ランキング1位に選ばれたこともあり、多くの観光客が訪れている。美しい庭園はもちろん、美術館の徹底した「おもてなし」の姿勢が評価されている。「庭園もまた一幅の絵画である」という信念のもと作られた庭園は、どこから見てもとても美しく、日本画のなかに入り込んだかのような錯覚に陥る。
「玉造温泉」は、島根県松江市にある温泉地。平安時代より三名泉とされてきた。約1300年前に「神の湯」として『出雲国風土記』に記載がある古湯。泉質は、「傷の湯」「脳卒中の湯」ともいわれている硫酸塩泉。
「松江しんじ湖温泉」は、島根県松江市の中心地近くにある温泉地。もともと「松江温泉」であったが、2001年に改名した。泉質は塩化物泉、硫酸塩泉で、肩こり、腰痛、婦人病などに効能があるといわれている。
「温泉津温泉」は、島根県大田市にある温泉。世界遺産の石見銀山の一角にあり、温泉地としては全国で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に指定された温泉地。1300年もの歴史を持つ古湯。泉質は、「美肌の湯」「清涼の湯」ともいわれる炭酸水素塩泉。
「出雲そば」は、出雲地方で食べられているそば。普通の傍と比べて色が黒っぽいのが特徴。冷たい「割子蕎麦」、温かい「釜揚げ蕎麦」がある。
「ぼてぼて茶」は、島根県出雲地方に伝わる料理で、立ったまま食べる労働食だったといわれる。乾燥した茶の花をいれ、煮だした番茶を茶わんに入れ、茶筅で泡立てる。お茶の中に煮豆やおこわ、高野豆腐などを少しずつ入れて食べる。
「うずめ飯」は、島根県西部の山間部で食べられている郷土料理。一見ワサビが添えられたお茶漬けのように見えるが、ごはんの下に刻んだ鯛や野菜が隠れている。野菜を煮込んだ汁の上にご飯を乗せている。
実は出雲はぜんざいの発祥地。出雲地方の「神在餅」に起因しているといわれている。旧暦10月は出雲では「神在月」といわれ、「神在祭」が執り行われる。その際に振る舞われるのが「神在餅」。じんざい→ずんざい→ぜんざいと呼ばれ方が変化していった。
島根県安来市は、どじょうすく踊りの発祥地で、全国屈指のどじょう養殖地。安来市内ではどじょう料理を味わえる店が多く存在する。安来市のどじょうは短期育成されるため骨が柔らかくて食べやすい。
「どじょう掬いまんじゅう」は、安来節に合わせて踊る「どじょう掬い踊り」のひょっとこお面をモチーフに作られたお菓子。
平安時代、慈覚大師円仁が遣唐の帰途立ち寄った際に唐で召し上がった羊の肝料理の話をされた。それを再現した料理が「清水羊羹」になった。
島根の和菓子老舗店、桂月堂が販売している「薄小倉」。上品な甘みの味わいが人気。
| 県名 | 島根県 |
|---|---|
| 人口 | 690,000人 |
| 面積 | 6,708km2 |
| 県の木 | 黒松 |
| 県の花 | 牡丹 |
| 公式HP | 公式ページへ |